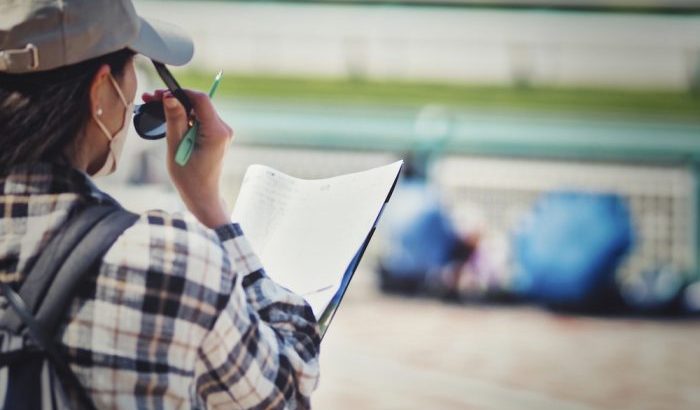「神社の歴史に非常に興味がある」
「神社とお寺の違いは?」
「伊勢神宮にある神社本庁についていろいろ知りたい」
日本には様々な神様が存在するといわれています。
基本的には日本人は無宗教の人が多いのもですが、そのような無宗教の人であっても、毎日仏壇の前でお線香をあげて、手を合わせるような行為をすることがあります。
日本人は信心深いといわれることもありますが、お寺や神社などに参拝に行った場合には、お賽銭を投げて手を合わせる行為を誰でも一度はしたことがあるのではないでしょうか。
お賽銭を投げて手を合わせる意味
お賽銭を投げて手を合わせると、願いが叶うという言い伝えがありますが、これはお賽銭と交換に願いをかなえてもらうという考え方です。
ですからお賽銭に投げる金額が大きいほど、効果があるという考え方もあります。
つまりそれはお金ではなく、少し怖い話ですが願いをかなえるためには、小銭よりも自分の髪の毛や爪をささげるような考え方もあるようです。
ですが、その考え方は少し怖いので、やはり手っ取り早い小銭を投げて、願いをかなえるという方法が理にかなっています。
特に神社などではお賽銭を投げる行為を行うことが多いでしょうが、そもそも「神の社」というものはなぜ作られることになったのでしょうか。
その歴史はかなり古いものです。
あわせて読みたい
神社本庁 – 公益財団法人 日本宗教連盟
神社の歴史
その昔の日本では、あらゆるすべての物には「神様」が宿ると考えられてきました。
その中でも特に巨木や大来な岩、他にも山などはとくに一目置かれる存在でした。
巨木や岩、山などには崇高な神が降臨される特別な場所である、と考えられていたのです。
そして、その神様に宿られるものは、神様として拝め奉られるのです。
そして神様が降臨された場所というのはその後で、「特別な場所」と認定され、神聖なる場所として他の地域と区別して、縄を張ったり石で囲いを作ったりしたのが神社の起源とされています。
そして西暦710年に日本は「奈良時代」に入りました。
すると「律令制度」というものが作られました。
それは全国にいっぱい祀られた神の社というものは大切な場所であったために、奈良朝廷は神社を組織にすることにしたのです。
このように歴史は古く、奈良時代にはその原型が作られましたが、実はもっと古くからあったのです。
それは古代までさかのぼります。
古代中世の時代から山や岩、巨木には神が宿るという考え方が根付いていたというのです。
このような考え方は神道に基づきます。
神道の発祥の地
この神道の発祥の地は壱岐の月読神社が、日本神道発祥の地であるといわれています。
神道という考え方自体は、縄文時代や弥生時代にまでさかのぼることと言われているのです。
それくらい歴史が古いのです。
日本人は前述のように無宗教の人が多いですが、信心深さだけは昔からあったようです。
ですが一つ気になることが出てきます。
神の社以外にもお寺というものもあります。
この二つは似ているようですが違いがあるのです。
どのような違いがあるのでしょうか。
神社とお寺の違い
まず神の社ですが、これは前述の通り神道ですが、お寺は仏教になります。
それが一番の大きな違いと言えます。
他にも見た目で異なる点が存在しているのです。
例えば、お寺は仏像やお墓がありますが、神の社は鳥居があるのが一番の特徴と言えるのではないでしょうか。
そもそも「仏教」とは、古来の中国やインドなどといった諸外国から、日本に伝来された宗教になります。
その一方で「神道」は日本が起源とされている宗教です。
上記のように山や石、他にも神木といった自然物を信仰します。
神道では、この世にあるさまざまなものに神様が宿るという考え方から「八百万の神々」といわれることもあります。
このように「仏教」であれ「神道」であれ、どちらの考え方も我々日本人にとってみると、とてもなじみがあるものですね。
仏教でも神道でもどちらの神様にもお祈りすることができる
日本人は仏教であれ、神道であれどちらの神様にもお祈りすることが出来ます。
例えば毎年年明けには「神社」に必ず参拝するという人も多いですし、人が亡くなった場合の通夜やお葬式では、「仏教」のやり方でおこなうことも多いです。
このように考えていくと、たくさんの神様や仏様に守られているような気がしてきます。
どこか特定の宗教に入っている場合には、その宗教以外の神様や仏様に手を合わせることは禁じられているような場合もありますが、もしも無宗教であれば、自由にお寺や神の社を参拝することが出来ます。
特に神の社では様々な神様がいるため、その神様の数だけ社があるという考え方です。
そのため、日本には様々な神の社があるのです。
赤い鳥居をくぐり参拝したら、そこの神様だけを崇拝する必要はありません。
どこの神の社に行っても、丁寧に頭を下げてお賽銭を投げて、祈ればよいのです。
まとめ
そうすれば様々な神様が助けてくれる可能性もあります。
あまりにもたくさんの神様を信仰してしまうと、神様同士でけんかをしそうなイメージもありますが、日本にはたくさんの社がありますので、社めぐりをするのも楽しいかもしれませんね。
その時にはたくさんの賽銭用の小銭を用意いていった方がよいかもしれません。